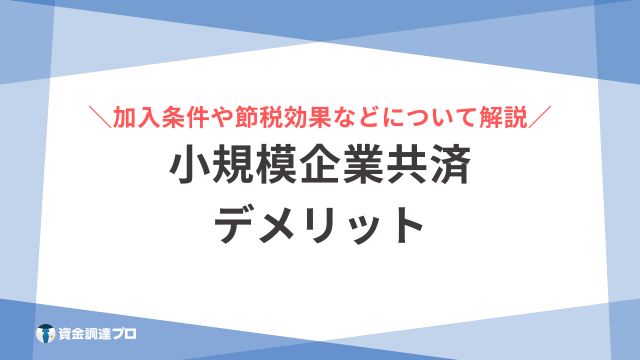小規模企業共済のデメリットとは?節税にならない?危ない・潰れると言われる理由や加入資格とメリットを徹底解説
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者・個人事業主・役員などに向けた退職金制度のことです。
毎月共済金を積み立て、解約時に退職金代わりとして、共済金を受け取る ことができ、昭和40年に発足してから、2023年3月末時点で加入者が162万人を超えています。
しかし、小規模企業共済には掛け捨てや元本割れのリスク、共済金は課税対象などデメリットもあるため、加入を悩んでいる事業者の方も多いです。
今回は、小規模企業共済に加入するメリット・デメリットや加入資格などについて詳しく解説していきます。
記事では小規模企業共済が危ない・潰れると言われる理由や節税にならないなどの疑問についてもまとめているので、小規模企業共済に興味のある事業者の方は参考にしてください。
小規模企業共済で積み立てた場合のシュミレーションから退職金をいくら受け取ることができるのかの目安 を知ることができますよ!
また、 24時間対応・最短即日入金もできるので、資金繰りを改善したい人におすすめ!
→今すぐ事業資金を確保する
目次
小規模企業共済とは?
小規模企業共済法に基づいて昭和40年に発足し、2023年3月末時点では162万人の加入が存在しています。
小規模企業共済に加入すると毎月共済金を積み立て、解約時に共済金を受け取ることができます。
退職金制度のない小規模企業の経営者や個人事業主のために向けた制度になります。
小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づいた掛金を支払うと、支払った掛金の全額が所得控除されます。
所得控除は全15種類あり、「小規模企業共済等掛金控除」はそのうちの一つです。
小規模企業共済は老後資金を積み立てつつ、掛金は全額控除できるため節税効果が期待できるという利点があります。
小規模企業共済の掛金は1,000円~70,000円(500円単位)で設定可能
小規模企業共済の掛金は1,000円~70,000円まで500円単位で設定できます。
さらに加入後であっても増額や減額をできるため、非常に自由度が高い制度と言えます。
経営状況によって掛金を設定できるので、 万が一、経営状況が悪くなっても無理のない範囲で減額して支払うことが可能です。
小規模事業共済の加入資格
小規模企業共済は小規模企業の経営者・個人事業主・役員などが対象となります。
「個人事業主」「個人事業主の共同経営者」「会社等役員」の加入資格について見ていきます。
小規模企業共済制度に加入できる個人事業主
・個人で建設・製造業、卸売・小売業などを営んでいる方
・理容・美容室などのサービス業を個人経営している方
・個人タクシーや、その他の運送業を個人で営んでいる方
・個人で農業を営んでいる方
・法人化していない個人医院、弁護士・税理士などの士業の方
小規模企業共済制度に加入できる個人事業の共同経営者
・共同経営者の地位で加入する方は、事業主の方と一体となって事業の経営に携わっていることが前提となります。
・申込者が経営に携わっている事業を営む個人が、小規模事業者であること。
・事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担している方。
・業務の執行に対する報酬を受けている方。
小規模企業共済制度に加入できる会社等役員
・株式会社、有限会社、特例有限会社の取締役または監査役の方。
・合名会社、合資会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員)。
・「業務執行社員」として登記されている合同会社の社員。
・企業組合、協業組合の理事または監事の方。
・農業の経営(営利目的)を主として行う農事組合法人の理事または監事の方(非営利を主とするものを除く)。
・士業法人の業務執行社員の方。
上記に該当する場合でも、事業を兼業している給与所得者や生命保険外務員、小規模企業者に該当しない事業を兼業していると加入できません。
詳しい小規模企業共済制度の加入についてはこちらから確認できます。
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済制度のデメリットは以下の通りです。
- デメリット① 掛金納付期間が12ヶ月未満は掛け捨てリスクがある
- デメリット② 20年未満の任意解約は元本割れするリスクが高い
- デメリット③ 共済金は受け取り時に課税される
それぞれ解説していきます。
デメリット① 掛金納付期間が12ヶ月未満は掛け捨てリスクがある
通常、共済金は廃業や解約により受け取れる制度ですが、共済事由と納付期間によって共済が受け取れない場合があります。
| 共済事由 | 掛け捨てリスクがある納付期間 |
|---|---|
| 共済金A・B | 6ヶ月未満だと掛け捨てになる |
| 準共済金 | 12ヶ月未満だと掛け捨てになる |
| 解約手当金 | 12ヶ月未満だと掛け捨てになる |
| A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人事業主 | ◎個人事業の廃止(※1) (注)複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を 廃止したことが条件となります。 ◎個人事業主の死亡 |
◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を 納付した方は請求することにより受給権を得ま す) |
◎法人成りし、その会社の役員に就任しなかっ た(※4) ◎法人成りし、その会社の役員に就任した(役 員たる小規模企業者となったときを除く)(※4) |
◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除 (12か月以上の掛金滞納等) ◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業 者となった(※4) |
| 共同経営者 | ◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任 (※2) (注)事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのす べての事業を廃止したことが条件となります。 ◎共済契約者の死亡 ◎共同経営者の疾病又は負傷による退任 |
◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を 納付した方は請求することにより受給権を得ま す) |
◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がそ の会社の役員に就任しなかった ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がそ の会社の役員に就任した(役員たる小規模企業 者となったときを除く) |
◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除 (12か月以上の掛金滞納等) ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がそ の会社の役員たる小規模企業者となった ◎共同経営者の退任による解約 |
| 会社等役員 | ◎会社等の解散 (注)組織変更により会社を解散した場合を除きます。 |
◎会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退 任(※3) ◎会社等役員の死亡 ◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を 納付した方は請求することにより受給権を得ま す) |
◎会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・ 死亡・解散を除く) |
◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除 (12か月以上の掛金滞納等) |
引用:小規模企業共済制度~説明用資料~|中小機構
「共済A・B」は個人事業の廃業や共同経営者の退任、65歳以上で180ヶ月間掛金を納付した場合に受け取れる共済金になります。
共済金A・Bに該当し、6ヶ月未満で解約すると掛け捨てとなり共済金は受け取れません。
一方で、「準共済金」と「解約手当金」は法人成りや任意解約により受け取れる共済金のことです。
準共済金と解約手当金に該当し、12ヶ月未満で解約すると掛け捨てとなるため共済金は受け取れません。
デメリット② 20年未満の任意解約は元本割れするリスクが高い
小規模企業共済制度を20年未満で途中解約すると、解約手当金が掛金合計額よりも下回り、元本割れになる可能性があります。
解約手当金は掛金の納付期間に応じて支給率(80%~120%)が変わります。
| 掛金納付期間 | 支給率 |
|---|---|
| 12ヶ月~83ヶ月 | 80.00% |
| 84ヶ月~89ヶ月 | 80.50% |
| 120ヶ月~125ヶ月 | 85.00% |
| 180ヶ月~185ヶ月 | 92.5% |
| 240ヶ月~245ヶ月 | 100.00% |
| 246ヶ月~251ヶ月 | 100.25% |
| 474ヶ月~479ヶ月 | 109.75% |
| 480ヶ月 | 110.00% |
| 720ヶ月以上 | 120.00% |
上記の納付期間と支給率を見てわかる通り、2年未満(240ヶ月未満)は支給率が100%未満です。
しかし、 納付期間20年未満で元本割れになるのは任意解約した場合のみです。
デメリット③ 共済金は受け取り時に課税される
共済金を一括で受け取ると「退職所得」、分割で受け取ると「公的年金等の雑所得」扱いになるため課税されます。
ただし、 退職所得の場合は税制上の優遇があるため税負担は重くありません。
共済金を分割で受け取った場合も「公的年金等の雑所得扱い」となり、こちらも控除が受けられるため節税につながります。
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済のメリットは以下の通りです。
- メリット① 退職金代わりになる(掛金の最大120%が戻ってくる)
- メリット② 掛金は全額所得控除されるので節税効果がある
- メリット③ 個人事業主は解約時の税負担が軽減される
- メリット④ 共済金の受け取り方法は「一括」か「分割」の2種類
- メリット⑤ 掛金の範囲内なら低金利で貸付制度を利用できる
それぞれ解説していきます。
メリット① 退職金代わりになる(掛金の最大120%が戻ってくる)
小規模企業共済は退職金として利用できるため、事業が廃業したときや老後の備えに最適な制度です。
掛金の納付期間に応じて支給率は異なりますが、最大で掛金の120%を共済金として受け取ることができます。
メリット② 掛金は全額所得控除されるので節税効果がある
小規模企業共済の掛金は全額所得控除される、つまり掛金は必要経費として事業の利益から差し引くことができるので高い節税効果が得られます。
支払った掛金は確定申告の際に「小規模企業共済掛金控除欄」に記入すると全額所得控除となります。
共済金の掛金は1,000円~70,000円まで設定できるため、年間で12,000円~840,000円の所得控除を受けることが可能です。
メリット③ 個人事業主は解約時の税負担が軽減される
小規模企業共済の共済金を受け取る際に課税されるとお話しましたが、 個人事業主が解約した場合は税負担が軽くなります。
個人事業主の場合は以下のような場合に共済金を受け取ることが可能です。
| 共済金の種類 | 請求事由 |
|---|---|
| 共済金A | 個人事業主を廃業、共済契約者の方が亡くなった場合 |
| 共済金B | 老齢給付 65歳以上、180ヶ月以上掛金を払っている |
| 準共済金 | 個人事業を法人成りして加入資格がなくなった場合 |
| 解約手当金 | 任意解約、機構解約など |
「個人事業主で退職金を用意するのは難しい」と考えている人も多いかもしれませんが、小規模企業共済を活用すればいざという時に役立ちます。
メリット④ 共済金の受け取り方法は「一括」か「分割」の2種類
共済金は一括受け取り、もしくは分割受け取りから選択できます。
共済金の受け取り方法を選択できるのは便利ですが、一括の場合は「退職所得」、分割の場合は「公的年金等の雑所得」扱いになるので注意が必要です。
分割受け取りの期間は「10年分割」と「15年分割」から選ぶことができ、一括よりも受取総額が多くなるメリットがあります。
分割受け取りの方がお得に思えるかもしれませんが、一括受け取りの退職所得扱いだと控除額が大きくなることがあるため、一概にどちらの方がお得なのか断言はできません。
また、分割受け取りの場合は「共済金A」もしくは「共済金B」のどちらかに限り、他にも以下の条件を満たさなければ分割受け取りはできません。
- 共済金A、または共済金Bに該当する
- 60歳以上
- 共済金の支払額が300万円以上
他にも、一括受け取りと分割受取の併用も可能ですが以下の条件を満たす必要があります。
・共済金Aまたは共済金Bである
・請求事由が共済契約者の死亡ではない
・請求事由が発生した日に60歳以上である
・共済金の受け取り額が、分割受取りは300万円以上、一括・分割併用で受け取る場合は330万円以上(一括受取りが30万円以上、分割受取りが300万円以上)
メリット⑤ 掛金の範囲内なら低金利で貸付制度を利用できる
小規模企業共済では貸付制度が用意されており、納付した掛金合計額の範囲内で貸付制度を利用できます。
| 貸付の種類 | 利率(年利) |
|---|---|
| 一般貸付け | 1.5% |
| 傷病災害時貸付け | 0.9% |
| 創業転業時貸付け | 0.9% |
| 新規事業展開等貸付け | 0.9% |
| 福祉対応貸付け | 0.9% |
| 緊急経営安定貸付け | 0.9% |
「一般貸付」の場合は事業資金や生活資金として利用できる上に、迅速に借入できる制度です。
特別な事情がある場合に借入できる「特別貸付」も充実しており、緊急時に便利な制度と言えます。
金利は一般貸付で年1.5%、他の貸付だと年0.9%と低金利なのも魅力的です。(※利率は金利情勢等を踏まえて設定される。)
万が一、返済が滞ると年14.6%の延滞利子が発生するため、延滞や滞納せずに計画的に返済してくださいね。
小規模企業共済の加入方法と必要書類
この章では小規模企業共済の加入方法と必要書類について以下の3STEPで解説します。
加入する人の地位によって手続き方法は異なるため、誤りがないように注意しつつ手続きを進めてくださいね。
STEP1 必要書類の準備と記入
| 小規模企業共済加入時の必要書類 | 必要書類一覧 |
|---|---|
| 個人事業主の場合 | 確定申告書の控え |
| 法人(株式会社など)の役員の場合 | 役員登記されていることが確認できる書類 |
| 共同経営者の場合 | 個人事業主の確定申告書の控え 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し 報酬の支払い事実が確認できる書類” |
| 中小機構の様式書類 | 契約申込書(様式 小 101) 預金口座振替申出書 |
引用:加入手続き|中小機構
それぞれの必要書類を揃えて、契約申込書と預金口座振替申出書に必要事項を記入して押印をします。
加入手続きは「窓口」と「オンライン」から可能で、窓口から加入手続きする場合の必要書類については資料請求から取得可能です。
オンラインで希望する場合は以下の方法で手続きが完了します。
- 中小機構のメールアドレス登録からメール登録を行う
- 加入手続き画面のURLが届いたらアクセスして、マイナンバーカード読込をする
- 必要事項を入力し、書類をアップロードする
- 掛金引落口座の設定をする
- 資格審査が実施される
- 審査結果通知と契約証書の送付
続いて窓口から手続きする場合の方法を解説していきます。
STEP2 窓口に書類を提出し、手続する
小規模企業共済の加入手続きを行っている窓口は、 中小機構と業務委託契約を締結している団体と金融機関に限ります。
小規模企業共済の加入手続きを受け付けている窓口は以下の通りです。
| 中小機構が業務を委託している団体(委託団体) | ・商工会 ・商工会議所 ・中小企業団体中央会 ・事業協同組合 ・青色申告会 ・損害保険ジャパン株式会社 ・アクサ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 中小機構が業務を委託している金融機関(代理店) | ・都市銀行 ・信託銀行 ・地方銀行 ・第二地方銀行 ・商工組合中央金庫 ・信用金庫 ・信用組合 ・農業協同組合(35都道府県) |
窓口で手続きできる金融機関から加入手続きを受け付けている金融機関を確認できます。
必要書類を持参の上、対象窓口まで足を運び手続きを済ませます。
STEP3 申し込みから40日後に中小機構から書類を受け取る
小規模企業共済の加入手続きが完了すると、約40日後に中小機構から「共済手帳」と「加入者のしおり及び約款」が届きます。
小規模企業共済加入後は、加入手続き時に希望した納付方法で掛金を支払います。
- 毎月払い
- 半年払い(加入月と加入月の6ヶ月目が指定納付月となる)
- 年払い(加入月が払込指定月となる)
ただし、現金納付の場合は加入手続き時に現金が必要となります。
口座振替の場合は、加入月の翌々月に3ヶ月分をまとめて口座振替となります。
小規模企業共済は公式より加入シュミレーションが可能
小規模企業共済の公式サイトにある加入シミュレーションにて、
将来的に受け取れる共済金と節税効果を確認できます。
加入シミュレーションの方法は以下のステップで試算が可能です。
試算条件の入力
- 加入年月日
- 現在の年齢
- 小規模企業共済を脱退するときの予定年齢
- 毎月の掛金の額
- 課税される所得金額
- 「試算する」をクリックする
課税所得金額600万円:30歳~60歳(30年)、毎月掛金3万円の場合
実際に小規模企業共済の加入シミュレーションで試算していきます。
今回は以下の条件でシミュレーションします。
- 現在の年齢 30歳
- 脱退時の年齢 60歳
- 毎月掛金 3万円(掛金合計額:10,830,000円)
- 課税所得金額 600万円
加入シミュレーションの試算結果は以下の通りです。
【受け取れる共済金(一括)】
| 共済金の種類 | 受け取れる共済金 | 実質返戻率 |
|---|---|---|
| 共済金A | 13,076,400円 | 174% |
| 共済金B | 12,676,200円 | 168% |
【節税効果】年間節税額 109,500円/年
| 加入の有無 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 加入前 | 788,700円 | 605,000円 | 1,393,700円 |
| 加入後 | 715,200円 | 569,000円 | 1,284,200円 |
【受け取れる共済金(分割)】※源泉徴収前
| 共済金の種類 | 10年分割 | 15年分割 |
|---|---|---|
| 共済金A | 228,837円 | 156,917円 |
| 共済金B | 221,834円 | 152,114円 |
小規模企業共済の実質利回り(運用利回り)について
令和4年度の小規模企業共済の運用利回りは0.36%でした。
画像引用:現況|小規模企業共済
内訳としては、自家運用資産が0.85%でやや低下気味ですが安定的で、委託運用資産が1.43%とボラタイルに変動しています。
| 運用損益額(億円) | 運用利回り(単純平均) | |
|---|---|---|
| 運用資産全体 | 1,600 | 1.59% |
| 自家運用資産 | 813 | 0.99% |
| 委託運用資産 | 787 | 4.60% |
出典:小規模企業共済資産 令和4年度の運用状況|中小機構
小規模企業共済では、小規模企業共済法で定められた基本方針に基づき運用されています。
個人事業主が小規模企業共済以外で老後資金を貯めるには?
個人事業主が老後資金を貯める方法は以下の3つが効果的です。
- 節税効果のあるiDeCo
- 途中解約ができる新NISA
- 受け取れる年金が増やせる国民年金基金※脱退不可
個人事業主で老後の備えに不安を感じている人も多いと思いますが、対策はあるので活用していってくださいね。
節税効果のあるiDeCo
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| iDeCoのメリット | ・全額所得控除されるため節税効果が得られる ・資産運用で得た利益は非課税になる ・月5,000円から1,000円単位で設定可能 |
| iDeCoのデメリット | ・老齢給付金を受け取れる年齢は原則60歳以降 |
iDeCoで積み立てた掛金は全額所得控除の対象になるため節税効果があり、個人事業主にぴったりな年金制度です。
資産運用で得た運用益が非課税かつ、受け取りの際も退職所得控除か公的年金等控除扱いになるため税負担が軽減されます。
ただし、iDeCoは老齢給付金を目的としているため、原則60歳以上でなければ給付金を受け取れないため注意が必要です。
途中解約ができる新NISA
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 新NISAのメリット | ・資産運用と老後資金の形成を効率的に行える ・非課税期間が無期限化になり、いつでも投資が可能 ・途中解約ができる |
| 新NISAのデメリット | ・投資の自由度が高く難しい ・18歳未満は口座開設できない |
新NISAは2024年からスタートしたNISA制度で、非課税期間が無期限になったため長期運用が可能になりました。
新NISAでは資産運用を効率的に行えるだけでなく、いつでも途中解約ができるため必要なときに現金が入ります。
老後の資金作りを目的とするiDeCoとは違い、NISAは資産形成の支援を目的にしているため「いざという時にお金が欲しい」という人におすすめです。
ただし、新NISAは自由度が高い一方で投資判断が難しく、初めての人は慣れるまでに時間がかかるかもしれません。
受け取れる年金が増やせる国民年金基金※脱退不可
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 国民年金基金のメリット | ・会社員との格差を解消して公的年金を補完できる ・税制上の優遇が受けられる ・終身年金 ・掛金額が一定で年金額が確定する |
| 国民年金基金のデメリット | ・加入すると脱退できない |
国民年金基金は自営業やフリーランスに向けた年金制度であり、会社員のように公的な年金を上乗せできるメリットがあります。
個人事業主などは会社員のような厚生年金がないため、老後資金が不足した場合に自分で補わないといけません。
国民年金基金ではそのような会社員との格差を解消できる上に、終身年金のため一生涯年金を受け取れるため老後の貯えが可能です。
国民年金基金の掛金は「全額社会保険料控除」の対象となるので、所得税や住民税も軽減されます。
加入すると任意で脱退できないのがデメリットですが、老後の生活を守るために優遇された制度と言えます。
小規模企業共済のデメリットに関するよくある質問
小規模企業共済に関するよくある質問に答えていきます。
- Q:小規模企業共済が潰れる可能性はありますか?
- Q:小規模企業共済が危ないと言われる理由はなんですか?
- Q:小規模企業共済は何歳まで加入できますか?
- Q:小規模企業共済はどこで加入できますか?
小規模企業共済のデメリットに関して深掘りしているので、加入を検討している人は参考にしてくださいね。
Q:小規模企業共済が潰れる可能性はありますか?
小規模企業共済は「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しており、国が全額出資しているので潰れるリスクを心配する必要はないです。
Q:小規模企業共済が危ないと言われる理由はなんですか?
加入期間が20年未満で任意解約した場合、解約手当金が掛金よりも少なくなるため元本割れしてしまいます。
上記でも紹介したように「共済金A」「共済金B」「準共済金」に関しては、2年未満で解約した場合は元本割れすることはありません。
また、小規模企業共済の共済金を受け取った際は課税されるため「危ない」と言われていますが、 「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いになるため控除を受けられます。
Q:小規模企業共済は何歳まで加入できますか?
小規模企業共済制度の加入条件を満たしていれば、どなたでも加入できます。
Q:小規模企業共済はどこで加入できますか?
| 中小機構が業務を委託している団体(委託団体) | ・商工会 ・商工会議所 ・中小企業団体中央会 ・事業協同組合 ・青色申告会 ・損害保険ジャパン株式会社 ・アクサ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 中小機構が業務を委託している金融機関(代理店) | ・都市銀行 ・信託銀行 ・地方銀行 ・第二地方銀行 ・商工組合中央金庫 ・信用金庫 ・信用組合 ・農業協同組合(35都道府県) |
詳しい取扱金融機関についてはこちらから確認できます。
オンライン手続きも可能なので窓口まで足を運べない人や、スピーディーに加入手続きをしたい人におすすめです。
小規模企業共済のデメリット まとめ
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金制度になります。
個人事業主は会社員とは違い、退職金がないため自ら退職金を用意する必要があります。
小規模企業共済は事業が廃業した場合や老後資金として利用できるため、いざという時の備えになります。
年齢制限はないため加入条件を満たしていれば加入でき、節税効果も高いため「将来に不安がある」という人におすすめです。
また、 24時間対応・最短即日入金もできるので、資金繰りを改善したい人におすすめ!
→今すぐ事業資金を確保する
昨日は0人が資金調達チェックの無料診断をしました。
今日は0人が資金調達チェックの無料診断をしました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。